遺言書の作成手続を、どこよりも安く、そして親切・丁寧な対応を心がけています。
 遺言書のサポート料金 (消費税別) 遺言書のサポート料金 (消費税別)
・安心の料金体系
公正証書遺言を作成する場合は、公証人役場への料金が別途かかります。
また、最初の御相談の時に総額の料金についてお示しし、納得の上でサポートをさせていただきます。
遺言書の作成で何度お客様のお宅等へ行くことになっても、上記以外の料金はいただきませんので、安心して御依頼ください。
当所の料金は、他の事務所と比べても格安で請け負っておりますので、安心して御依頼ください。
また、セトナ事務所では、料金が安いだけではありません。サポート体制も充実しております。
、埼玉県:さいたま市、川越市、上尾市及びその近隣の方で相続・遺言書に関することなら、セトナ相続・遺言サポートセンターにお任せください。
電話、Eメールでのお問い合せは無料です。また、遺言書の作成の御相談は、出張相談料も無料ですので、お気軽に御依頼ください。
TEL: 0493−54−4148
E-mail: setona@rz.main.jp
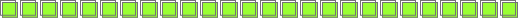
 遺言とは 遺言とは
遺言とは、自分が死んだときに備え、法に定める一定の様式に沿って、自己の財産の処分や、身分上の事項、遺言執行に関する事項についての意思を表示するものです。
これにより、例えば通常なら相続人が協議で定める遺産分割の内容を、自ら指定したりすることができます。また、相続人が財産を取得するのに一定の条件を付けたり、相続人以外の人に財産を取得させたり、特定の相続人が取得する財産を遺留分の限度にしたりできます。
 遺言が必要な理由 遺言が必要な理由
遺言を残さずに死亡した場合、遺産は民法の定める法定相続分に応じて相続人に分割されることになります。
例えば、亡くなった方が、家業を継承している長男に法定相続分より多く遺産を相続して欲しいと望んでいた場合、遺言を遺しておかなければ長男が他の相続人より多く相続できるかどうかは他の相続人との協議次第となってしまいます。
相続は金銭や権利関係が絡むものであり、相続問題がこじれてしまうと、仲の良かった家族間でさえ協議が難航するという事態に陥ってしまう事もありえます。家族間にヒビが入るような種をまかないようにきちんと事前に対応策を考えておくことが大切です。
 遺言書に書く内容 遺言書に書く内容
基本的には遺言書は遺産相続のために作成されるものですが、それ以外にも書くことは可能です。しかし、あくまでも遺産相続についてが目的ですので、すべての内容が内容通りに行われるわけではありません。
例えば、「長男○○は、私が死んだら実家で暮らすこと」なんて書かれていたとしても、そういったことは法律内では何ともならないため、法律上では意味がありません。
もちろん、家族に対して意思を示すことができるという点ではよいと思いますが、あくまでも遺産相続が目的の書類であるため、新たに他の書類を作って書くなり、遺言ではなく直接手紙を書くなりして伝えればいいことです。
そのようなことを遺言書に書いても、法律上は問題ありませんが、その通りになるわけではありませんので注意が必要です。
 遺言書の残し方 遺言書の残し方
遺言書は一定の書き方が決められており、その書き方に則っていない場合には、遺言自体が無効となってしまいます。
ここにいう無効とは、法的な効力を有さないという意味です。つまり、法的な部分において遺言はまったくその意味をなさず、単に手紙としての効力しか有さない書面となってしまいます。
単に自分の意向を相続人に対して示したい、つまり自己の死後に備えた手紙としての効力でよいのであれば、適宜の様式で記載しても何ら問題はありません。
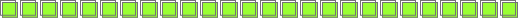
 自筆証書遺言 自筆証書遺言
遺言者が自分で遺言内容の全文、日付及び氏名を自書し、署名の下に押印して作成する遺言を自筆証書遺言といいます。
公証人の手を借りることなく、手軽に作成できる遺言書ですが、その効力は公正証書遺言と変わりません。
【注意点】
自筆証書遺言は、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされています(民法968条1項)。
この規定のとおり、自筆証書遺言は、全て手書きで作成する必要があります。
そのため、例えば本文をパソコンで作成したり、家族に書いてもらったりして、サインだけ自分でするという方法は認められません。
また、1度作成した自筆証書遺言を変更する場合には、遺言者が変更「場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ」なりません(民法968条2項)。
これらの方式に違反した遺言は無効となってしまいます。
 公正証書遺言 公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言自体は公証人が作成するため、特に専門家に相談せずご自身で手続きをとることも可能です。
ただし、戸籍謄本や財産に関する資料はご自身で用意しなければなりませんし、作成したい遺言の内容もご自身で公証人に伝えなければなりません。
また、遺言内容をどのように実現するかについて、別途考えておく必要もあります。
ご自身で手続きをとれば、費用は、公証役場での作成費用のみですので、費用の節減になることは間違いありませんが、その分手間がかかることも間違いありません。
 秘密証書遺言 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできる遺言です。まず、遺言書を作成し、封印、証人二人とともに公証人の面前で、自分の遺言書である旨等を申述します。しかし、内容については公証人が関与しないため、法定内容について争いになる可能性もあります。
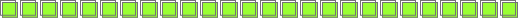
 遺言書の検認 遺言書の検認
*遺言書の検認の概要
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
*申立人
*申立に必要な費用
- 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出を求められることもあります。
【共通】
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
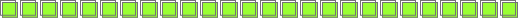
 家族のため遺言書を作成してください。 家族のため遺言書を作成してください。
どんなに仲の良かった家族でも、ちょっとした感情のもつれから相続トラブルは起こります。また、遺言を残しておかなかったばっかりに、今まで住んでいた家を失うこともあります。
遺言の目的はいろいろですが、大切な家族を無用なトラブルから守ること、これが遺言の最も大きな役目です。
※こんな人はぜひ遺言を!
・夫婦の間に子供がいない。
配偶者とともに、親や兄弟が相続人になり、もめるケースが多い。
・音信不通の子供がおり、どこにいるかわからない。
遺産分割ができなくなってしまう。
・嫁に財産をあげたい。
・内縁の妻に財産をあげたい。
・事業を継ぐ長男に事業用の財産を譲りたい。
・財産を譲りたくない息子がいる。
・障害のある子どもに多くの財産を残したい。
|
|
相続・遺言書に関する出張相談も承ります。埼玉県内4,500円です。
ただし、遺言書等を御依頼の場合は、出張相談料は無料です。
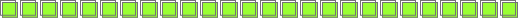
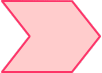 法律用語としての遺言 法律用語としての遺言
遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいいます。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多いですが、このうち民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされています。(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多いです。
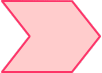 改めて遺言が必要なわけ 改めて遺言が必要なわけ
どんなに仲の良かった家族でも、ちょっとした感情のもつれから相続トラブルは起こります。また、遺言を残しておかなかったばっかりに、今まで住んでいた家を失うこともあります。
遺言の目的はいろいろですが、大切な家族を無用なトラブルから守ること、これが遺言の最も大きな役目です。
※こんな人はぜひ遺言を!
・夫婦の間に子供がいない。
配偶者とともに、親や兄弟が相続人になり、もめるケースが多い。
・音信不通の子供がおり、どこにいるかわからない。
遺産分割ができなくなってしまう。
・嫁に財産をあげたい。
・内縁の妻に財産をあげたい。
・事業を継ぐ長男に事業用の財産を譲りたい。
・財産を譲りたくない息子がいる。
・障害のある子どもに多くの財産を残したい。
|
|
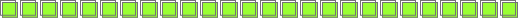
|
