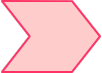 遺産分割協議書とは 遺産分割協議書とは |
被相続人が遺言書を残していればそれに従って財産を分割します。
しかし、遺言書が無かった場合、また遺言書はあってもそこに記載のない財産がある場合は、相続人全員が相談して、誰が何を相続するかを決めていくことになります。その話し合うことを「遺産分割協議」といいます。作成される書類が遺産分割協議書です。
「不動産は長男が相続する。株券は次男が相続する。絵画は妻が相続する。」と決めて、後々もめないように書面にしっかり作成します。
亡くなった人の財産は、その人が亡くなった瞬間に相続人全員の共有となります。共有とは、所有権などについて複数の人によって所有されていることです。
セトナ相続サポートセンターでは、埼玉県内の相続や遺産分割協議書の作成サポートを格安でお引き受けしています。
|
 遺産分割協議書の作成料金等は次のとおりです。(消費税別) 遺産分割協議書の作成料金等は次のとおりです。(消費税別) |
◆自筆証書遺言の作成サポート
◆生前贈与(相続時精算課税)
◆公正証書遺言の作成サポート
◆遺産分割協議書の作成
◆相続人調査
◆相続お任せパック |
38,000円
贈与額の0.9%(最低12万円)
45,000円
42,000円〜
25,000円
相続財産の0.9%(最低15万円) |
|
 |
 遺産分割とは 遺産分割とは
相続が開始して相続放棄も限定承認 をしないで3カ月が過ぎると、単純承認したことになり、被相続人が死亡時に有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同相続することになります。 この遺産の共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配し取得させる手続きを、遺産分割
といいます。
 遺産分割の時期等 遺産分割の時期等
遺産分割の時期については、相続開始後であればいつまでにしなければならないという期限はとくにありません。被相続人が遺言で分割を禁止していないかぎりいつでも自由に分割を請求することができます。
しかし、相続税の配偶者の税額軽減の適用は遺産の分割が前提となっていますし、また、あまり時間が経ちますと遺産が散逸したり、相続の権利のある関係者が増えていくなど、複雑になってきますので、なるべく早い時期に分割協議を行うべきです。
なお、遺言があり、そこに遺産の分割方法の指定がされている場合には、それに従うことになります。しかし、遺言にすべての財産についての分割方法が指定されていれば問題ありませんが、分割方法の指定のない財産については、やはり相続人全員の話合いで分け方をきめなければなりません。
 遺産分割の手続き 遺産分割の手続き
遺言による分割
被相続人が遺言で分割の方法を定めているときは、その指定に従って分割します。また、遺言で分割の方法を第三者に委託することもできます。
協議による分割
遺言がない場合や、あっても相続分の指定のみをしている場合、あるいは、遺言 から洩れている財産がある場合には、まず、共同相続人の間の協議できめます。相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はありません。、また、ある人の取得分をゼロとする分割協議も有効とされています。
調停・審判による分割
協議がまとまらないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。家庭裁判所への請求は調停、審判のいずれを申し立てても差し支えありませんが、通常はまず調停を申し立てることがほとんどです。調停が成立しない場合は当然に審判手続きに移行します。

 遺産分割協議書の作成サポート 遺産分割協議書の作成サポート
セトナ相続サポートセンターでは、、遺産分割協議書の作成サポートを行っております。
遺産分割協議に必要な以下の手続きをすべて代行します。
- 亡くなられた方の戸籍謄本等の収集
- 相続人の戸籍謄本等の収集
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
これらすべての手続きを代行して、報酬は42,000円〜です。

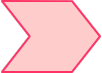 遺産分割の基準となる相続分が民法に定められている。 遺産分割の基準となる相続分が民法に定められている。 |
相続分には、民法が定める法定相続分と被相続人が遺言で定める指定相続分の2つがあります。
なお、法定相続分より指定相続分が優先されます。
法定相続分
民法では次のとおり法定相続分を定めています。
なお、配偶者はいつでも相続人となります。
第1順位; 配偶者 1/2 子 1/2
第2順位; 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
第3順位; 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
同順位の血族が複数いる場合の分割割合は、等分になります。
ただし、非嫡出子は嫡出子の2分の1であり、半血兄弟は兄弟の2分の1となります。
指定相続分
遺言により、法定相続分とは異なった相続分を指定することができます。被相続人自身が築き上げてきた財産ですので、原則として自由に相続分を指定することができます。
ただし、相続人には最低限留保された遺留分という制度がありますので留意が必要です。 |
 |
|
